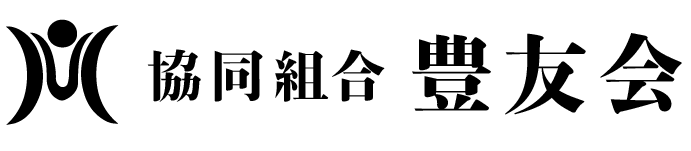9月6日から8日に、東京支部の定例研究会で秋の河骨(こうほね)をいけました。河骨を手配いただいた産地から髙橋農園(千葉県君津市)の髙橋伸行さん・綾子さんご夫妻が訪れ、菊池瑞月支部長の案内のもと、研究会の現場を見学されました。
秋の河骨を研究会で利用しました
菊池 秋の研究会の花材に、河骨を利用させていただきました。ご準備をありがとうございました。
髙橋(伸) 育てている河骨が作品になる様子を拝見できて、とても嬉しかったです。
菊池 今年の研究会の年間計画で、9月の一級家元教授の表現が写景盛花自然本位だったんです。水ものを扱いたいと考えていた時に、自然本位で河骨の実を使ってみたら面白いのではと思い、ご相談させていただきました。
髙橋(綾) 普段の研究会で、河骨をいけることは多いのですか。
菊池 写景盛花様式本位のお稽古などで夏の黄色い花をいけますが、秋の実をいける機会は少なくとてもよい経験でした。8月の夏季特別研究会でも水ものの講習を行ったのですが、その時から1か月の間でも、河骨の姿に微妙な変化があって。季節ごとに植物の変貌を表現できることは、小原流いけばなの魅力と改めて感じました。
髙橋(伸) 今回、実に限らず、盛りで咲く黄色い花、朽ちてきて赤みがかった花なども用意してみました。
菊池 自然本位の表現なので、同じものが一つとしてないのがよかったです。そこがいけ手にとっての醍醐味(だいごみ)であり、挑戦であったりしますから(笑)。
髙橋(綾) 私たちは実際に河骨をいけたことがなく、出荷の際に迷うことがあります。例えば、ここ数年の酷暑で日焼けした葉、虫に喰われた葉などは破棄してしまうのですが、さまざまないけ方が
あることが分かりました。
菊池 葉の先端などであれば自然本位なら使える場合もあります。お稽古の内容から生花店と利用者で相談し合って、ロスを減らしていけるとよいですね。他に課題はありませんか。
髙橋(伸) お盆を過ぎると利用が減って河骨を採らないため、圃場(ほじょう)で葉が混んでくるんです。そうなると、葉が小さく育ってしまうという悩みがあります。
菊池 コンスタントな利用が大切ですね。私たちも秋の河骨をいける楽しさを再認識できましたら来年は他の支部の皆さんにもぜひトライしていただきたいです。最後に、髙橋さんが感じる河骨の魅力を聞かせてください。
髙橋(綾) 水面に浮かぶ濃緑の葉からのぞく鮮やかな黄色の花、そこからだんだんと朽ちてきて赤色に変化する光景はとても美しいです。
菊池 緑色の蕾(つぼみ)も可愛いですよね。魅力ある花を今後もぜひ利用させてください。
引用:豊友会たより2025年11月号より